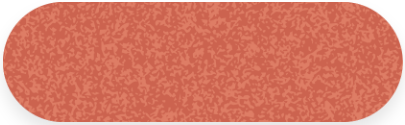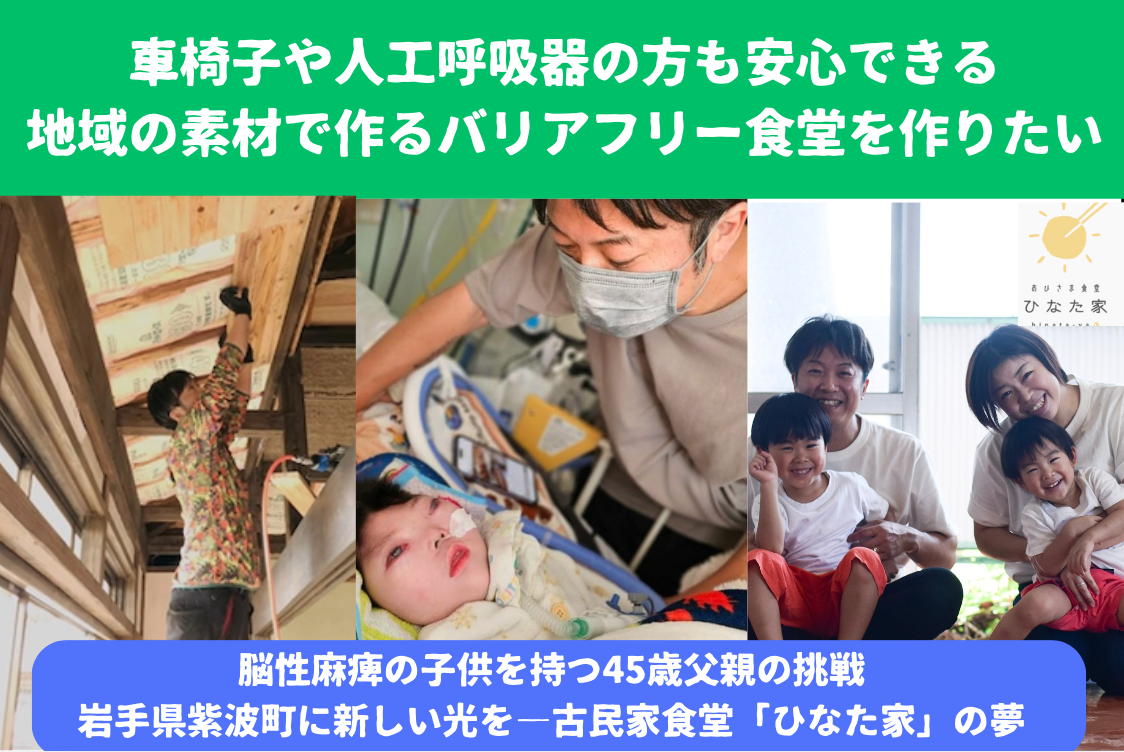「現代風金継ぎ」をやってみたら、暮らしの質が高まった

みなさん、こんにちは!
slowz編集部です。
今日は、slowz編集部から金継ぎ体験レポートをお送りします。
皆さんのお家に、ひびや欠けがあり使えなくなった食器類はありますか?
私の家には、お気に入りだったものの一部欠けてしまい、とはいえ捨てる気にもなれない...といった皿類がいくつか眠っていました。
そういった皿類をもう一度使えるようにするため、”兎と寅”さんで提供されていた金継ぎ体験にslowz編集部が参加してきました。
今回参加したのは、伝統的な材料を使わず、パテや新漆を使いどなたでも簡単にできるようにアレンジした「現代風金継ぎ」です。
金継ぎとは?
割れや欠け、ヒビなどの陶磁器の破損部分を漆によって接着し、金などの金属粉で装飾して仕上げる修復技法。金繕い(きんつくろい)とも言います。
時代は古く、戦国時代から用いられていた修理手法です。
壊れた器類に金継ぎにより新たな魅力を加えながら再利用できる状態にすることで、同じものを長く使い続けることができる点で、サステナブルな生活の知恵といえます。
▼出典
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E7%B6%99%E3%81%8E
実際に体験してきました!
今回は花瓶、小皿、ボール皿の3種の金継ぎを行いました。
作業ステップは大きく分けて下記3つです。
①足りない部分を埋める。
②はみ出た部分を削る。
③継ぎ目に金を塗る。
①足りない部分を埋める。
本体とパーツの間の隙間を埋めるために、接着剤を塗布し、ガラスの粉を振りかけていきます。後工程ではみ出た部分は削るので、どんどん埋めていきます。
②はみ出た部分を削る。
①で補った部分で、器から浮き出ている箇所を、彫刻刀を使って削っていきます。慣れないときは多めに削ってしまって、また①の工程に戻って...ということを繰り返しつつ、少しずつ表面を平坦にしていきます。学生時代の美術の時間を思い出します。
③継ぎ目に金を塗る。
細い筆を使って、継ぎ目に金を塗っていきます。最初は慣れない細かな手作業で緊張しましたが、綺麗な線をひけると、いよいよ”金継ぎ”らしくなってきました。
(下記写真中央にある、左上から右下に伸びている金色の線が金継ぎ箇所)
金継ぎした作品はこのような仕上がりに。
元々の器の青さに金が差し色になって、一層魅力的になったように感じます。
(器の右上が金継ぎ箇所)
体験を終えて
金継ぎしたお皿をまじまじと見てみると、以前にも増して愛着が増した感覚があります。「サステナブルな選択」という面だけでなく、「日本伝統工芸の体験」も同時に得られたことも良かったです。
これをきっかけに、「使えなくなったら新しいものを買う」のではなく、「直して使う」選択肢をより日常に取り込みたいなと思います。
今回金継ぎ体験したslowz掲載店舗
普段はお酒のセレクトショップとして営業されており、不定期でイベント開催もされているそう。
〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目25−11
※イベント開催状況は公式HPにてご確認ください。
https://usatora.tokyo/